430MHzトランスバーター
Last Modified at
オークションでサーキット・ハウスの50→430MHzトランスバーター"CV-607A"を3100円で入手しました。

これは50MHz帯の数Wの入力信号を430MHz帯(出力は200mW)に変換するもので、2年ほど前まで定価7800円で売られていたものです(説明書の後には1998-03-20と日付が記述されています)。現在(2001年11月)はCQ誌等を見ると同じ値段で"CV-607B"という2枚基板ものにバージョンアップされているようです。
組み立ては結構厄介で、まず説明書に詳しい記述があまりありません。回路図と部品配置図をにらめっこしながら間違えないように実装してゆかなければなりません。
まずは部品面に真鍮のシールド板を組み立てます。これが結構大変で、手先の不器用なわたしには余りきれいに組み立てられませんでした。
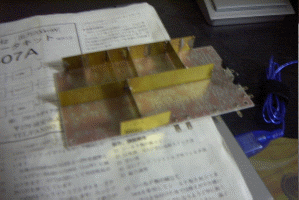
次に組み立て始めて気づいたのですが、2つある水晶発振部のトランジスタ(2SC2668)が1つとスイッチングダイオードが1つ足りません。ダイオードの方は手持ちの1S1588を使いましたが、トランジスタは手持ちにないのでとりあえず水晶発振部は1つしか動作しない状態で作業をすすめることにしました。
次に電源部と水晶発振部を実装しました。ここでまた重大な発見をしました。それは2つある水晶発振回路の一方の基板のパターンが間違っています。発振部出力のトランスの出力段の巻き線が本来PINダイオードに接続されるべきところがGNDに落っこちているのです。なんでこんな間違いがあるのかわかりませんが、とにかくトランスの出力側のまわりの基板をカッターナイフで削ってそこへ半田面からPINダイオードを半田付けしました。あとコンデンサを実装するべき場所に穴があいておらず、これも裏側(半田面)に実装しました。
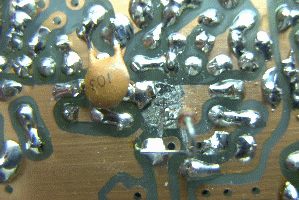
とにかく間違いが多いので、回路図とにらめっこしながら、正しいかどうかを常に照合しながら半田付けしてゆく必要があります。こんなんで最後までちゃんとできるかなぁ。まあ、そこが楽しいんだけど…。
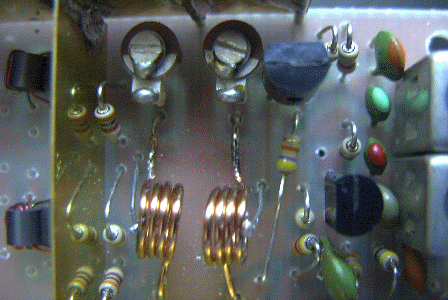 これは局発の最後のところのコイルです。二つの同じ形のコイルは手巻きですが、巻きかたが逆で、この2つのコイルのカップリングで最終的な380MHzの出力を得ます(42.22MHz×3×3)。信号は右から入り左へ抜けてゆきます。両方のコイルの真中辺りにはんだ付けされているリード線が入出力ですが、このリード線のはんだ付け位置が説明書を見てもよくわかりませんでした。実体配線図によると中間タップを取るような絵になっていますが、3回半巻いたエナメル線の途中からタップをとることは不可能なので、コイルの一番端のターンの頂上部の外側をカッターナイフで注意深く削って被覆を剥がし、そこにはんだ付けしています。これでいいのかなぁ。
これは局発の最後のところのコイルです。二つの同じ形のコイルは手巻きですが、巻きかたが逆で、この2つのコイルのカップリングで最終的な380MHzの出力を得ます(42.22MHz×3×3)。信号は右から入り左へ抜けてゆきます。両方のコイルの真中辺りにはんだ付けされているリード線が入出力ですが、このリード線のはんだ付け位置が説明書を見てもよくわかりませんでした。実体配線図によると中間タップを取るような絵になっていますが、3回半巻いたエナメル線の途中からタップをとることは不可能なので、コイルの一番端のターンの頂上部の外側をカッターナイフで注意深く削って被覆を剥がし、そこにはんだ付けしています。これでいいのかなぁ。
と思っていながら先の実装作業を進めてゆくと、トンでもないことに気付きました。このL7,L8はやっぱり正しくないのです。このL7,L8はどうも430MHzの出力のファイナルにあるBPFを構成する2つのコイル(回路図上でL8,L9)のようです。説明書にコイルの巻き方が書いてあり、それにはL7,L8と書かれており、しかもこのコイルは逆向きに巻くので、てっきり一対でトランスを構成するものなのだと勘違いしてしまいました。どうも実体図の絵と合わないし、妙だなとは思っていたのですが、こんな落とし穴があるとは……。だいたいL8が二つもあるのでそもそも変なのですが、最初にすべてをチェックしておかないと、この間違いには気付かないでしょう。
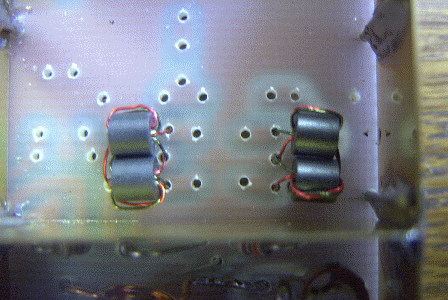 こちらの方は、上の局発出力が入力される送信用ダイオードミキサの前後のDBMトランスです。ここにも回路図と基板パターンに矛盾があり、50MHzの送信波が入る端子と、局発が入る端子が回路図と基板パターンおよび実体配線図で逆転しています。これはまあこれでもいいのかなぁ(というより回路図どおりにすることは不可能)なのでそのまま作業をすすめました。
こちらの方は、上の局発出力が入力される送信用ダイオードミキサの前後のDBMトランスです。ここにも回路図と基板パターンに矛盾があり、50MHzの送信波が入る端子と、局発が入る端子が回路図と基板パターンおよび実体配線図で逆転しています。これはまあこれでもいいのかなぁ(というより回路図どおりにすることは不可能)なのでそのまま作業をすすめました。
発見された間違いの数々……
- 汎用SWダイオードがない(欠品)。袋は開けていられなかったので前の持ち主が抜いたのではないと思われる
- トランジスタ(2SC2668)がない(欠品)。袋は開けていられなかったので前の持ち主が抜いたのではないと思われる
- 基板にC43をさしこむ一方の穴が開いていない
- 回路図のC42はC43の間違い
- 実体配線図上のトランジスタQ10(2SC1906)の向きが逆
- 基板にR39をさしこむ一方の穴が開いていない
- 発振回路出力部のコイル(T4)の出力側のパターンが誤っている
- DBMトランスT2への入力が回路図上の局発と送信機からの信号が実体図・実際の基板両方とも入れ替わっている
- 実体配線図上のR7が明記されていない
- 実体配線図上のR9が明記されていない
- 実体配線図上のR1とR2が逆
- 回路図・実体図の送信出力後のフィルタを構成するL8・L9がコイルの巻き方の図ではL7・L8となっている
- 回路図・実体図の局発出力後のトランスを構成するL7・L8がコイルの巻き方の図ではL9・L10となっている
- いくつかあるチップコンデンサ(1000p)が実体図上に書かれていない。書いてあるのもあるので余計ヤヤコシイ
というわけで、このキット、知識のあるわかった人がよっぽど注意深く(疑り深く)作らないと決して完成しない、というなかなか味のあるもののようです。このキットを設計した人は発売したキットをどうも一度も作っていないようです。できっこないもん。
(2001-12-9追加)
さて、気を取り直して続きをやりました。
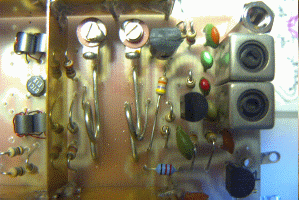 先ほどの間違えた局発出力用のコイルを正しいと思われるスズメッキ線1ターンのコイルに変更しました。そうすると、今度はちゃんと出力に380MHzの強い信号が現れました。変更後、局発2段目の3逓倍器を構成する2SC1906まわりのはんだ付けがおかしかったらしく、そこでもイロイロ苦労しましたが、結果的にはOKとなりました。
先ほどの間違えた局発出力用のコイルを正しいと思われるスズメッキ線1ターンのコイルに変更しました。そうすると、今度はちゃんと出力に380MHzの強い信号が現れました。変更後、局発2段目の3逓倍器を構成する2SC1906まわりのはんだ付けがおかしかったらしく、そこでもイロイロ苦労しましたが、結果的にはOKとなりました。
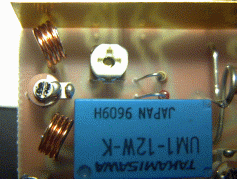 間違えていた0.7φエナメル線3回半巻きの2つのコイルは送信出力段のT型フィルタのものだったようです。サイズ的にもここならピッタリです。
間違えていた0.7φエナメル線3回半巻きの2つのコイルは送信出力段のT型フィルタのものだったようです。サイズ的にもここならピッタリです。
で、とりあえず受信系の実装は終わったので、まずSEND端子をグランドに落としたり(こうすると送信になる)、オープンにしたりして、リレーが切り替わる音がするのを確認しました。次にアンテナ入力に430MHzのアンテナを繋ぎ、トランシーバー側にはFT-690mkIIを繋ぎました。FT-690のダイヤルを回してゆくと……なんとFMで交信している局が聞こえました。ウーム。とりあえず受信はOKか?
ただここで1つ大きな問題が発生しました。100kHzおき位に酷いスプリアスが受信されます。これはアンテナを繋がないと聞こえないので外から拾っているような気もしますが、発振器のコイルのコアに金属性のドライバーで触るとやまったりします。でもこれは金属性のドライバーでコイルのコアに触れると、発振周波数が大きく変動することが原因とあとでわかりました。出力段のタンクコイルに触れるだけで周波数が動くのもちょっと妙な感じがしますが……。もう一つの384MHzを発振する発振回路の方はこのスプリアスはあまり聞こえてきません(ところどころでは聞こえる)。よくわからんなぁ。手持ちの430MHzのハンディ機と比べると受信感度はそんなに遜色ないような気がしました。全般的にまだ基板が裸の状態のせいかどうかわかりませんが、動作は非常に不安定です。
(2001-12-16追加)
これはおいといて、次に送信系をはんだ付けし終わりました。ようやくすべての部品を付け終わり調整に入ります。まずは最終段の消費電流が30mAとなるようにVRを調整しました。消費電流は受信時約70mA、送信時はVRを絞りきった状態で160mA(説明書では120〜140mAとあったので若干多い)、VRを調整して190mAにしました。
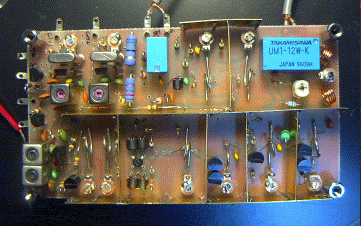
次に実際にトランシーバーを繋げて送信の調整をしようとしたのですが、なんとここでトランスバーターを受信状態にしたままトランシーバーを送信してしまいました。一発で受信系のGaAsFET(ソニー製SGM2006M)をとばしてしまいました(痛恨!!)。このFETを入手するまでは次の作業はおあずけ……(調べたら秋月で10個200円で売っているのを発見し、ひとまずはホッ)。
(2001-12-24追加)
とりあえず気を取り直して送信系の調整をしました。
 出力を見るとやはりDBMの入力のローカル(380MHz)と50MHzの送信波入力の入り口が入れ替わっているのがよくないようです。仕方がないのでまたもや基板を削って修正しました。なんでこんな間違いがあるのかなぁ。とにかくこの修正をした後、ようやく430MHz帯の送信出力が出るようになってきました。
出力を見るとやはりDBMの入力のローカル(380MHz)と50MHzの送信波入力の入り口が入れ替わっているのがよくないようです。仕方がないのでまたもや基板を削って修正しました。なんでこんな間違いがあるのかなぁ。とにかくこの修正をした後、ようやく430MHz帯の送信出力が出るようになってきました。
ところがまたまた問題が発生しました。430MHzの送信/受信切替え用の高周波リレー(TAKAMISAWAのUM1-12W-K)が壊れているようで、送受を切替えても送信出力が出る方へ切り替わりません。インターネットで高周波リレーをいろいろ調べたところ、オムロンのG5Y-1というリレーがサトー電気で540円で売っていてこれがピンコンパチのようです。秋葉原あたりへ行けば高見沢の同じ型番のリレーが手に入るのかも知れませんが、少なくともインターネット上では発見できませんでした。は〜。かなりめげてきました。
(2001-12-28追加)
オムロンのG5Y-1をサトー電気の通販で\540で買いました。それから秋葉原の秋月へ行ってSGM2006Mの10個200円を買って来ました。リレーを取り替えてトランジスタは念のため2つとも交換しました。そうしたらどうやら受信系は復活、リレーによる送受切替えもできるようになりました。送信系のトリマーを調節して(送信系のトリマーは結構クリティカル)、おそらく60mW〜100mW程度出力が出るような状態になりました。受信時の妙なスプリアスは、局発を所望波が強くなるように調整することで大分マシにはなりました。ただまだ問題があって、受信感度が悪く、受信系のトリマーに手で触ったり、調整用のドライバで触れたりするとよくなります。はんだ付けの不良かと思って結構念入りに調べましたがそうもその傾向は消えません。この辺、もう少しじっくり調べる必要がありそうです。
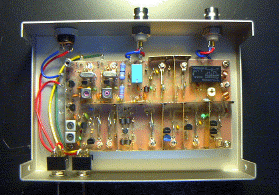
(2001-12-30追加)
受信系のスプリアスはどうも局発の廻り込みによる発振のような気がしています。ケースに入れてシールドを多少強化するとかなりマシになります。アンテナを繋いだ状態で受信段の初段のアンプの同調回路のトリマーを調節するとスプリアスの出方がかなり変わります。
 その後どうしても受信感度がよくならず(手持ちのハンディ機で聞こえる信号が聞こえない)、手で触れるとハンディ機と同等程度になるので、理屈もへったくれもなく最低の対症療法ですが、トリマーのステーター側にリード線の屑2センチ程をはんだ付けすると、感度が上がりました。根本的な解決になっていません。
その後どうしても受信感度がよくならず(手持ちのハンディ機で聞こえる信号が聞こえない)、手で触れるとハンディ機と同等程度になるので、理屈もへったくれもなく最低の対症療法ですが、トリマーのステーター側にリード線の屑2センチ程をはんだ付けすると、感度が上がりました。根本的な解決になっていません。
それまではずっと親機にヤエスのFT-690mkIIをつかっていましたが、TS-680Vの方で受信してみると、ダイヤルを回している最中に時々メーターが振りきれるような雑音が発生します。430MHz入力のアンテナ端子付近に手を近づけただけで妙なスプリアスが発生します。やはりなにか調子が悪く、どうも高周波増幅段が発振気味のような気がしています。ただこれも詳しく調べる術がなくそう思っているだけの状態です。
(2002-1-6追加)
その後、430MHz入出力部の基板とBNCコネクタの間(距離にして2〜3cm)をビニール線で繋いでいたのを1.5D2Vに換えてみると、受信感度が良くならない状態が若干改善し、トリマー付近を手で触れても状態が変わらなくなりました。TS-680受信時の妙な雑音も今のところ出なくなったようです。対症療法に付けていたリード線も外しましたが大丈夫のようです。ただ59で聞こえている信号が、アンテナを接続したコネクタあたりに手を触れたりするだけで突如ノイズレベル以下に下がったりと、依然として動作は不安定です。ところどころにある強力なスプリアスも相変わらずです。受信系がどうも発振気味のような気がしています。



 7m1kng@jarl.com
7m1kng@jarl.com


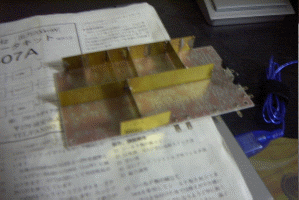
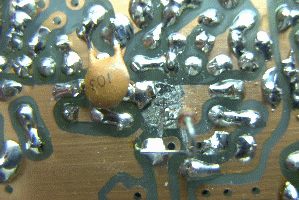
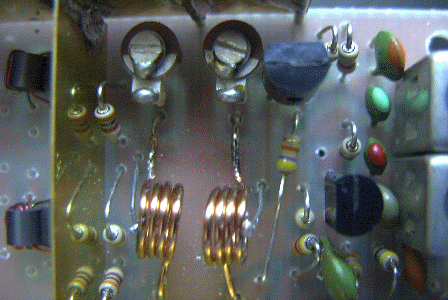
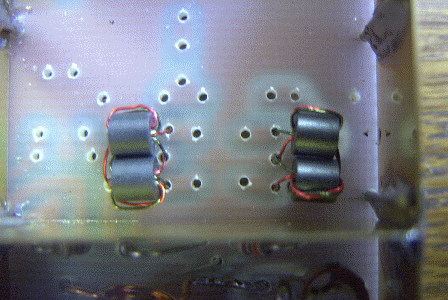
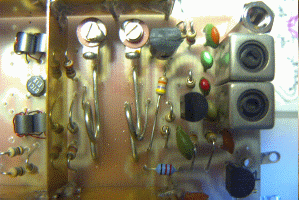
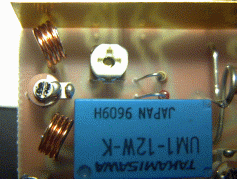
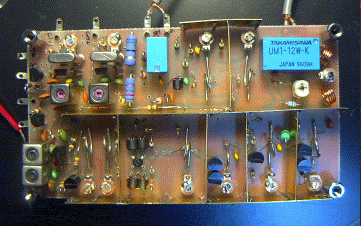

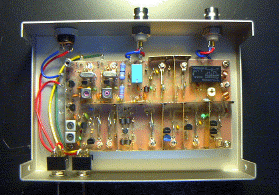




 7m1kng@jarl.com
7m1kng@jarl.com