トランスバーター局部発振部
Last Modified at
IFが11.272MHzのSSBジェネレーター部につなげるトランスバーターに挑戦しようと思ってまずはトランスバーターの局部発振部を考えてみました。
とりあへず50MHzのトランシーバーにしたいので、50MHz-11.272MHz=38.728MHzを作らなければなりません。まずは周波数可変部分に中古で手に入れたミズホのVFO-5を使うことにします。このVFOの発振周波数は5.0〜5.5MHzです。したがって38.728-5.0=33.728MHzを作る必要があります。手持ちの11.275MHzの水晶を使えば11.275×3=33.825MHzなのでなんとかなりそうです(ちょっときついか?)
つぎにVFO-5の出力を測ってみます。
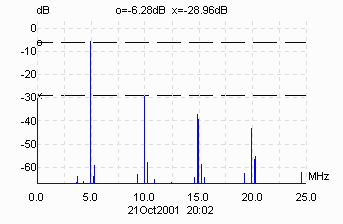 これはVFO-5の出力スペクトラムです。高調波レベルは2倍が強くてだいたい-23dBc、3倍が-31dBcくらいです。VFO-5にはハイインピーダンス出力と50Ω出力が用意されていますが、これはハイインピーダンス出力端にプローブを当てて測りました。
これはVFO-5の出力スペクトラムです。高調波レベルは2倍が強くてだいたい-23dBc、3倍が-31dBcくらいです。VFO-5にはハイインピーダンス出力と50Ω出力が用意されていますが、これはハイインピーダンス出力端にプローブを当てて測りました。
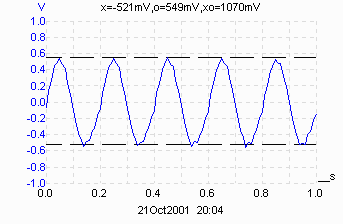 これはVFO-5の時間波形です。だいたい1Vpp程度です。この波形を取ったときは発振周波数は一番上でした。発振周波数ごとの出力レベルは測っていません。発振周波数は手に入れてなにも調整しない状態で、下が4.968MHz、上5.487MHzで可変範囲は521kHzでした。
これはVFO-5の時間波形です。だいたい1Vpp程度です。この波形を取ったときは発振周波数は一番上でした。発振周波数ごとの出力レベルは測っていません。発振周波数は手に入れてなにも調整しない状態で、下が4.968MHz、上5.487MHzで可変範囲は521kHzでした。
次にVFOと混ぜる水晶発振部の検討をします。11.275の3逓倍をしたいので、3倍オーバートーンの回路を試しに作ってみました。
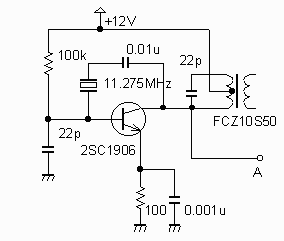 この回路は例によって「ビギナーのための……」の50MHzAM送信器の局発を作る部分のコピーです。どうも不安定で、FCZコイルのコアをうまく調整しないと5逓倍出力の方が(56MHz)が出てしまいます。バラックの空中配線で不安定な接続をしているせいもあると思います。
この回路は例によって「ビギナーのための……」の50MHzAM送信器の局発を作る部分のコピーです。どうも不安定で、FCZコイルのコアをうまく調整しないと5逓倍出力の方が(56MHz)が出てしまいます。バラックの空中配線で不安定な接続をしているせいもあると思います。
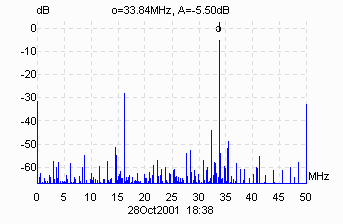 これが上の回路図のA点で測定した3倍オーバートーンで動作しているときのスペクトラムです。出力レベルは-5.5dB(約1Vpp)です。計算上の発振周波数は、11.275MHz×5=33.825MHzですが、周波数カウンターで測ると33.8455MHzでした。16MHz付近に大きなスプリアスが見えますが、なんなのかよくわかりません(もしかしたら高調波の折り返しかもしれませんが...)。高調波については測定につかったA/D変換器が100MHzのサンプリングレートのため分かりません。スペアナが欲しい!!
これが上の回路図のA点で測定した3倍オーバートーンで動作しているときのスペクトラムです。出力レベルは-5.5dB(約1Vpp)です。計算上の発振周波数は、11.275MHz×5=33.825MHzですが、周波数カウンターで測ると33.8455MHzでした。16MHz付近に大きなスプリアスが見えますが、なんなのかよくわかりません(もしかしたら高調波の折り返しかもしれませんが...)。高調波については測定につかったA/D変換器が100MHzのサンプリングレートのため分かりません。スペアナが欲しい!!
だけどどうも発振が不安定です。上のスペクトラムの波形も、プローブをタンク回路につなげるとうまく3倍オーバートーンで発振するのですが、離したりすると発振が止まったり、5倍に飛んだりします。よくよく調べてみるとこのプローブは並列容量が×10で14pF、×1だと47pFもあり、回路に対してかなり影響を与えてしまうことがわかりました。
 その後いろいろ試行錯誤の末、このような回路にして、出力をミキサとして使おうと思っているSN16913の5番ピンに接続すると、うまく3倍で発振することが分かりました。まずFCZコイルの並列コンデンサが22pFでは少し小さいことに気付き、もうひとつ22pFを並列にして44pFとしました。次に2次側の出力を0.001uFのコンデンサを介してSN16913につなぎました。またレベルが高すぎるので電源電圧を5Vまで下げてみました。
その後いろいろ試行錯誤の末、このような回路にして、出力をミキサとして使おうと思っているSN16913の5番ピンに接続すると、うまく3倍で発振することが分かりました。まずFCZコイルの並列コンデンサが22pFでは少し小さいことに気付き、もうひとつ22pFを並列にして44pFとしました。次に2次側の出力を0.001uFのコンデンサを介してSN16913につなぎました。またレベルが高すぎるので電源電圧を5Vまで下げてみました。
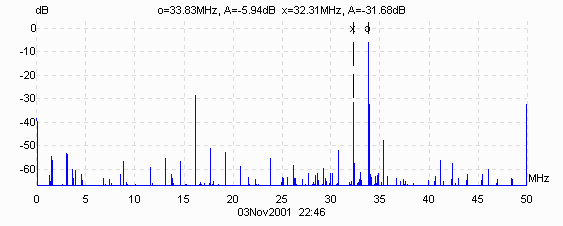 その時のSN16913入力のスペクトルがこの図です。レベルは約-6dB(約1Vpp)となっています。ちょっと強すぎますね。また脇に見える32.3MHzのスプリアスはこれは実は2倍高調波です(サンプリング周波数は100MHzなので、100-33.8×2=32.2MHz)。ただプローブの周波数特性が悪いので正確ではないと思います。それを考えないと、所望波に比べて2倍波のレベルは約-25dBcということになります。16MHz付近のスプリアスはまだ不明です。またSN16913につないだ状態だと、発振周波数が少し下がって33.839MHzくらいになりました。
その時のSN16913入力のスペクトルがこの図です。レベルは約-6dB(約1Vpp)となっています。ちょっと強すぎますね。また脇に見える32.3MHzのスプリアスはこれは実は2倍高調波です(サンプリング周波数は100MHzなので、100-33.8×2=32.2MHz)。ただプローブの周波数特性が悪いので正確ではないと思います。それを考えないと、所望波に比べて2倍波のレベルは約-25dBcということになります。16MHz付近のスプリアスはまだ不明です。またSN16913につないだ状態だと、発振周波数が少し下がって33.839MHzくらいになりました。



 7m1kng@jarl.com
7m1kng@jarl.com
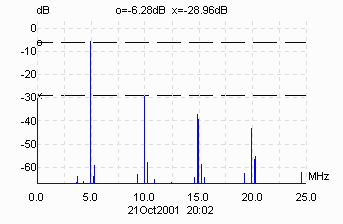
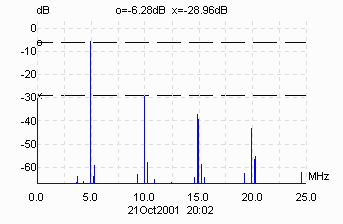
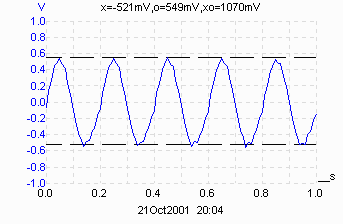
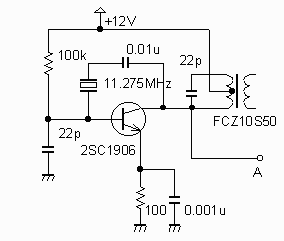
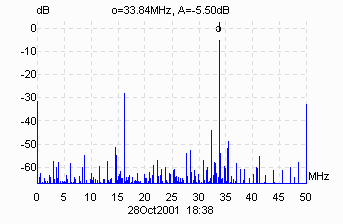

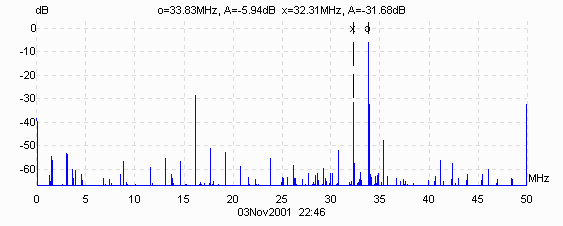



 7m1kng@jarl.com
7m1kng@jarl.com