7MHzダイレクトコンバージョン受信機
Last Modified at
JR7CRJ千葉秀明氏の本「ビギナーのためのトランシーバー製作入門AM・SSB編」を参考に7MHzのダイレクトコンバージョン受信機を作ってみました。最初は部品を集めてバラックで組み立てる予定でしたが、アイテック電子研究所に問い合わせたところ、プリント基板が入手可能とのことでしたので、通販で買いました。値段は\1,000でした(ちなみに同じ本に載っているSSBジェネレータの基板も\1,200で買ってしまいました)。
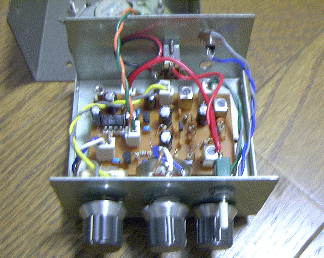
この受信機はRF増幅に2SK439一段、ミキサーも同じく2SK439、局発も同じく2SK439を使ったVFOという構成です。AF段は2SC1815+LM386Nとなっています。特殊な部品は敢えて挙げればFCZのコイルくらいで、他の部品は比較的簡単に手に入るものです。VFOの安定度がイマイチ(それは本の中にもそのように記述されています)で、SSBを聞いている分にはそんなに気になりませんが、CWではトーンがドンドン変化するのですぐわかります。
非常に再現性のよい回路で、VFOの安定度はもうひとつなのですが、大変聞き易い音質で、しかもバリコンのカバレッジが特に調整しないでもちょうど100kHz程度になっています。周波数全体の調整は必要ですが、それも局発に使っているFCZの7S7というコイルのコアをチョイといじってやるとすぐに所望(つまり7000から7100kHz)の周波数帯が受信できるようになります。

20年ほど前、高校のころに作ったモールス発振器の中身を出して、小さいケースにこの受信機を入れました。左のツマミがチューニング用のバリコン、真中がAFゲイン、右がRFゲインです。いずれもジャンクのTS-520から外したツマミです。チューニング用のツマミが小さすぎて選局がしずらいですが、デザイン上大きいツマミにするとカッコ悪くなりそうなのでとりあえずこのままです。
というわけで早速アンテナをつないで7MHz帯を受信してみました。全体の利得が若干低い所為か、簡単なアンテナではもうひとつ聞こえてきませんが、7MHzのダイポールをつなげると日本全国の交信がよく聞こえてきます。ただダイレクトコンバージョン方式の宿命で、キャリアの反対側の信号が抜けてくるため、混信が聴感上2倍になる、上側と下側ヘテロダインの区別がつかないのでチューニングが結構メンドウという欠点はあります。ただ実用上一番気になるのは放送波の抜けで、夜になると7140kHzも北朝鮮のピョンヤン放送がバンド中どこへまわしても聞こえてきます。これはマイッタ。
この受信機はアンテナ入力に10kΩのアッテネータ(写真の一番右のRFゲインのこと)がついていますが、夜間放送波が強い時間帯はこのアッテネータで入力信号を絞り込めばある程度放送波の抜けは緩和されることがわかりました。通り抜けといっても本当に通り抜けるわけではなくて、主たる原因は恐らくミキサーの2次歪と考えられるわけで、入力を下げれば当然歪も下がっていくというわけです。
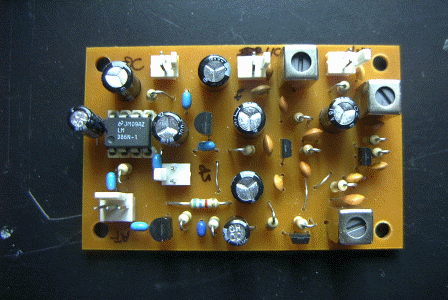
このダイレクトコンバージョン受信機の周波数変動を調べてみました。この図は2001年9月終わりの曇りの正午ごろに室温で測定しました。測定中の気温の変化はあまりなかったと思います。電源投入後最初の10分くらいは大きく変化しますが、概ね20〜30分で安定し、その後は1時間で100Hz程度しか変化しなくなっています。
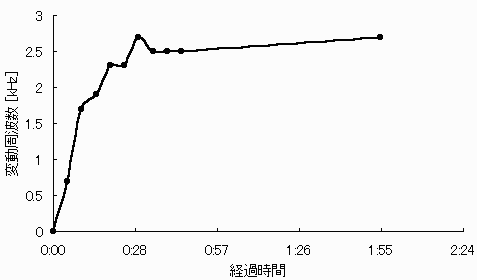
(2001-11-18追加)
しかしながら周波数安定度が悪すぎて、あまり実用的でないのでちょっと対策を施しました。対策の内容はVCOの共振回路を構成する15pF、33pF、0.001uFのセラミックコンデンサをスチロールコンデンサ(それぞれ部品入手の関係上15pF、30pF、0.0012uF)に変更したというものです。これで電源投入直後の大きな周波数変動はなくなりました。でもまだ安定してからも少しづつ周波数がドリフトします。特にCWを聞いていると、矢張り徐々にトーンの高さが変わってゆくのが気になります。もう少し発振用のトランジスタまわりも部品変更の必要がありそうです。



 7m1kng@jarl.com
7m1kng@jarl.com
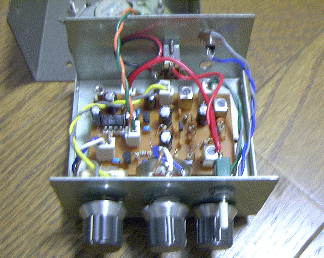
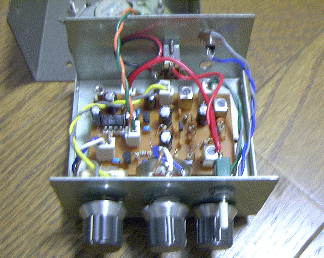

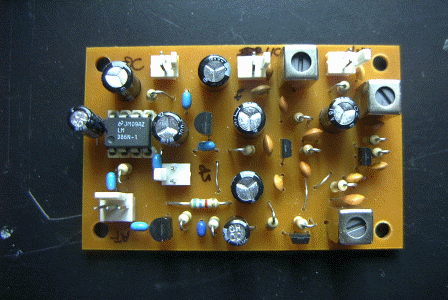
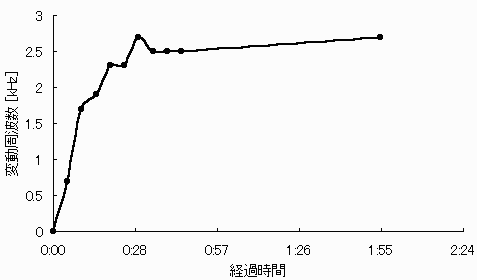



 7m1kng@jarl.com
7m1kng@jarl.com